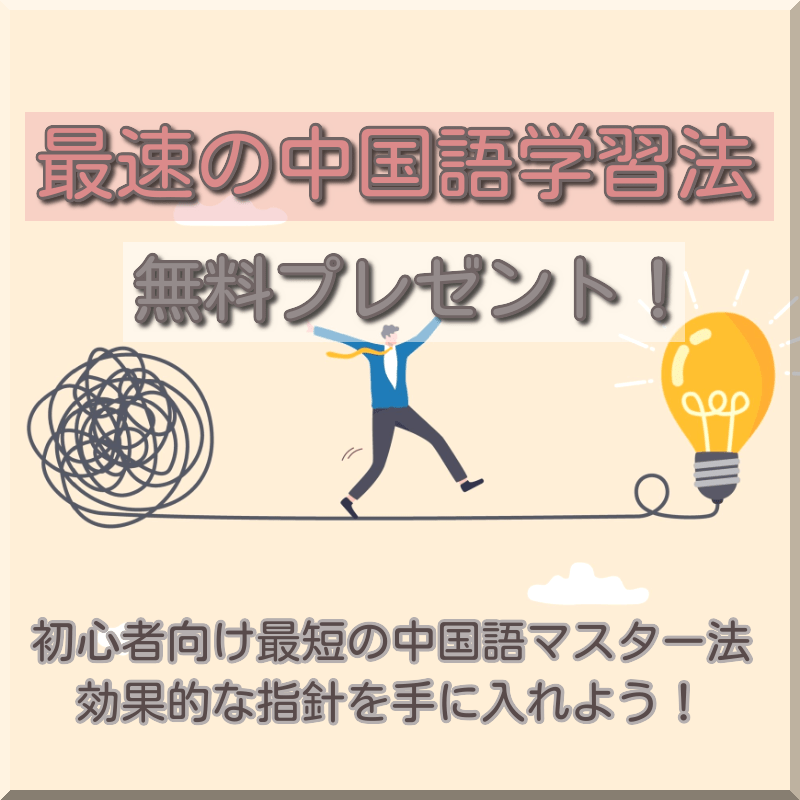中国の法定祝日は7日あります。
中国の祝日カレンダー:法定祝日とその背景
目次
中国の法定祝日
これまでお話しした春节(chūn jié)、国庆节(gúo qìng jié)、中秋節(zhōng qīu jiē)以外に、新年(xīn nián)、清明节(qīng míng jié)、劳动节(láo dòng jié)、端午节(duān wǔ jié)があります。
16日もある日本の法定祝日の半分以下ですが、その分、大掛かりなイベントが開催されます。ちょっと見てみましょう。
新年
新年(xīn nián)は新暦の1月1日、元旦です。この日は、ちょっと残念だったのですが、とくに街を挙げてのイベントや催しもなく、静かに過ごすことができました。
その後に控えた春节(chūn jié)が、やはり中国人にとって大切な新年の始まりなのですね。そのギャップが激しいです。
清明节
清明节(qīng míng jié)は、春分から数えて15日目です。この日は家族そろって先祖の「扫墓(sǎo mù:墓参り)」します。
お墓を掃除して、ごちそうなどを添えて、お参りですね。これを一言で表現するなら「扫墓祭祖(sǎo mù jì zǔ)」となります。
また、清明节は踏青节(tà qīng jié)」とも言われます。「踏青(tà qīng)」とは、郊外に出かけて自然の中で緑を楽しんだりするという意味。
だからなのか、お参りを済ませた後は、まるでハイキングに出かけるような感覚で、近隣の景色の良いところでお供え物を食べながら宴会を始めます。
墓地の周りには、宴会用のスペースを設けているところもあるそうです。
お墓にお供えするものですが、
①香烛(xiāng zhú):線香とろうそくです。
②纸钱(zhǐ qián):紙で作った紙幣です。冥钞(míng chāo)ともいいます。あの世でお金に困らないようにです。
③素酒(sù jǐu):僧侶が飲めるお酒のことで、葡萄酒(pú táo jǐu)や米酒(mǐ jǐu)のこと。米酒はもち米を使って作る透明な甘いお酒です。
④水果点心(shǔi gǔo diǎn xīn):果物とお菓子です。
⑤饭菜(fàn cài):ご飯とおかずです。故人が好きだったものを用意して、みなで故人を忍びながら食べて、下の代の者たちが故人を忘れないようにするのだそうです。
また地方によって特色があり、例えば上海では青团(qīng tuán)を食べます。これはスズメノチャヒキという植物の汁でもち米を練って、小豆やナツメの餡を包んで蒸して作った団子です。
山西では子福馍(zǐ fú mó)を食べます。馍(mó)はマントウのこと。
このマントウの中にナツメや小豆、クルミを包んで龍の形に整えて、龍の体に卵を差し込んで蒸します。これを子福(zǐ fú)というのだそうです。家族団らんの幸せを象徴します。
⑥鲜花(xiān huā):生花。菊の花が一般的。
⑦包袱(bāo fú):風呂敷を意味しますが、ここでは白い紙を使って作った袋を指します。中には、冥钞(míng chāo)や紙で作った元宝(yuán bǎo:馬蹄銀)や服、家具が入っています。
地方によって面白い習慣、迷信もあります。手術を受けたばかりの人は、簡単にあの世に連れていかれてしまうから墓参りに参加しない方がよい。
3歳になっていない子供も、その純粋な心のためか、墓地では簡単にあの世を垣間見てしまうため連れて行かない方がよい、そうです。
劳动节
劳动节(láo dòng jié)は5月1日です。この日は国際連合などが定めた国際的な記念日で祝日。日本ではお休みではありません。
端午节
端午节(duān wǔ jié)は、旧暦の5月5日です。名前の由来は、「端(duān)」は、「端っこ、つまり物の始まり」の意味で「初(chū)」に通じ、「最初の5」という意味で「端五(duān wǔ)」。
そのうち、「五(wǔ)」が「午(wǔ)」に通じることから「端午(duān wǔ)」。
その上、各月に十二支を当てはめると、ちょうど5月が「午(wǔ)」となり、5月5日は月も日も5であることから5月5日が端午节(duān wǔ jié)と言うようになったといわれます。
端午节(duān wǔ jié)は、春节(chūn jié:春節)、中秋节(zhōng qīu jié:中秋節)とともに中国の重要な祝日です。
端午节の起源
日本で端午の節句といえば、男児の健やかな成長を願って兜を飾ったり、鯉のぼりを上げたりする「こどもの日」ですが、中国の子供の日は6月1日となっています。
5月5日の端午节(duān wǔ jié)の起源は、有力な説の一つとして、楚(chǔ)の政治家で詩人の屈原(qū yuán)にちなむといわれています。
屈原(qū yuán)は、人望はあったものの失脚してしまい、汨罗江(mì lúo jiāng:汨羅江。湖南省の北東部を流れ、洞庭湖に注ぐ河川)に身を投げます。
それを悲しんだ楚(chǔ)の人々は舟を出して屈原の遺体を探しに出ましたが、洞庭湖(dòng tíng hú:洞庭湖)でその痕跡を失ってしまいました。
ちまきの訳
人々は、魚が湖の魚が屈原の遺体を食べないように、湖に粽子(zòng zǐ:ちまき)を放り込んだのだといいます。
そのため、中国でも端午节(duān wǔ jié)には粽子を食べます。
ドラゴンボートレースの由来にも
また、毎年5月5日に船を出して当時をしのぶようになったといいます。これも魚に屈原の遺体を食べられないように、舟で魚を散らすためだったそうです。
これが、今となって国際大会にもなった赛龙舟(sài lóng zhōu:ドラゴンボートレース)につながったのかもしれませんね。
南方や、北方でも湖や河川があるところでは、5月5日に赛龙舟が開催されます。

法定ではない祝日
中国では、伝統的な祝日以外にも、国際デーを取り入れたり、国の成り立ちや考え方にかかわる出来事を記念する祝日もあります。
中国の記念日
そのへんを垣間見ていると、中国という国の背景に何があるのか見えてくるような気がします。数ある記念日の中でも、祝日というお休みにこだわってちょっと散策してみましょう。
国际劳动妇女节(gúo jì láo dòng fù nǚ jié)
国际劳动妇女节は太陽暦の3月8日です。1909年3月8日、アメリカのニューヨークで女性労働者が参政権を求めてデモを行ったことを記念して始まった国際デー。
中国ではこの日、女性だけが「放半天假(fàng bàn tiān jiǎ:半ドン)」です。職場によっては、上司が女性職員に昼食代をあげたり、何か記念品をプレゼントしたりすることもあります。
中国らしい呼び方には「三八节(sān bā jié)」「三八妇女节(sān bā fù nǚ jié)」があります。
中国で初めて婦人デーを祝ったのが1924年の3月8日、広州でのこと。第一次中共合作の最中で、両党とも女性の労働の解放を重視していたそうです。
中国の強い女性たち
あらゆる場面で女性が強い中国らしいですね。
吴仪
中国の強い女性として、みなさんは誰を思い浮かべますか?私は、女性政治家の吴仪(wú yí:呉儀)さんです。
彼女は小泉元首相との面談をドタキャンして帰国してしまった印象が強烈でしたが、2006年、米経済紙「福布斯(fú bù sī:フォーブス)」の「世界に最も影響力のある女性100」では、ライス国務長官(当時)に次いで第3位でした。
2002年に非典(fēi diǎn:SARS)が猛威を振るったとき国務院SARS予防部で指揮を振ったのが吴仪さんでした。
郎平
もう1人います。郎平(láng píng:郎平)さんです。排球迷(pái qíu mí:バレーボールファン)ならご存じですね。選手や監督としての実績は申し分ありません。
でも、私が郎平(láng píng)さんの強さというか不気味さを感じるのは、監督として、試合がどんな状況にあっても表情一つ変えないところです。
精神力の強さですね。さすがワールドワイドに活躍した人だけあります。
中国青年节
(zhōng gúo qīng nián jié)
中国青年节は太陽暦の5月4日で、14歳以上の若者は「放半天假(fàng bàn tiān jiǎ)」です。
この节日(jié rì)の起源は1919年に遡ります。第一次世界大戦終結後の巴黎和会(bā lí hé hùi:パリ講和会議)でのこと。
中国側は山東省ドイツ権益の継承などについて日本が突き付けた「二十一条(èr shí yī tiáo:対華21か条要求)」の無効を主張するも退けられてしまいました。
すると北京では、この結果に抗議して学生3000人以上が示威游行(shì wēi yóu xíng:デモ行進)を行い、これが全国に拡大していったのでした。
日本に関する記念日
抗日、反帝国主義、反封建主義という思想を解放した新文化運動といわれます。あまり大っぴらには言えませんが、中国には日本に関する記念日が結構あります。
お休みではありませんが、戦時の屈辱を忘れないようにするためなのでしょうね。
7月7日:中国人民抗日战争纪念日
(zhōng gúo rén mín kàng rì zhàn zhēng jì niàn rì:中国人民抗日戦争記念日)
1937年7月7日、日中戦争に突き進むことになる卢沟桥事变(lú gōu qiáo shì biàn:盧溝橋事変)が勃発した日です。
北京郊外の卢沟桥(lú gōu qiáo)には中国人民抗日战争纪念馆(zhōng gúo rén mín kàng rì zhàn zhēng jì niàn guǎn:中国人民抗日戦争記念館)があって、7月7日に訪問したのですが、無料で開放されていました。
9月3日:中国抗日战争胜利纪念日
(zhōng gúo kàng rì zhàn zhēng shèng lì jì niàn rì:中国抗日戦争勝利記念日)
1945年9月2日、日本がポツダム宣言による降伏文書に調印した日。
連合国軍の多くはこの日を戦勝記念日としているが、中国とロシアでは9月3日を記念日としています。
9月18日:九一八事变纪念日
(jǐu yī bā shì biàn jì niàn rì:九一八事変記念日)
1931年9月18日、満州事変の端緒となる柳条湖事変(lǐu tiáo hú shì biàn:柳条湖事変)が勃発した日です。
その後関東軍は中国東北部を全面的に占領下に置きました。中国国辱の日。
12月13日:南京大屠杀纪念日
(nán jīng dà tú shā jì niàn rì:南京大虐記念日)
1937年12月13日、日本軍が南京を陥落して入場。その後、何が起こったのか今も議論粉分です。
このほか、対日だけではなく、他にもあります。
12月12日:西安事变纪念日
(xī ān shì biàn jì niàn rì)
1936年12月12日は、张学良(zhāng xué liáng)と杨虎城(yáng hǔ chéng)が蒋介石(jiǎng jiè shí)を拉致監禁し、内戦停止を迫った西安事变(xī ān shì biàn)を記念する西安事变纪念日(xī ān shì biàn jì niàn rì)です。
5月9日:驻南联盟大使馆被炸日
(zhōng gúo zhù nán lián méng dà shǐ guǎn bèi zhà rì:中国駐ユーゴスラビア大使館爆破日)
5月9日は、旧ユーゴスラビアで1999年5月9日(現地時間)にコソボ紛争におけるNatoの空爆作戦で中国大使館が誤爆された日。
中国驻南联盟大使馆被炸日(zhōng gúo zhù nán lián méng dà shǐ guǎn bèi zhà rì:中国駐ユーゴスラビア大使館爆破日)です。
われわれも、愚かな過ちを繰り返さないように、過去の惨劇は後世に引き継いでいかなければなりませんね。
国际儿童节(gúo jì ér tóng jié:国際児童デー)
国际儿童节は6月1日。14歳未満の少年児童は1日のお休みがもらえます。
新中国成立前の儿童节(ér tóng jié)は4月4日でしたが、のちにそれを破棄して、国際デーと同じ6月1日に儿童节を設定しました。
ただ、香港と台湾はいまだに4月4日が儿童节です。
中国人民解放军建军纪念日
(zhōng gúo rén mín jiě fàng jūn jiàn jūn jì niàn rì:中国人民解放軍建軍記念日)
中国人民解放军建军纪念日は8月1日です。現役軍人は「放半天假(fàng bàn tiān jiǎ)」です。
1927年8月1日、国民党軍を攻略した南昌蜂起を機に中国人民解放军(zhōng gúo rén mín jiě fàng jūn)の前身である中国工农红军(zhōng gúo gōng nóng hóng jūn:中国工農紅軍)を成立させた日。
新中国成立後に、中国人民解放軍建軍(zhōng gúo rén mín jiě fàng jūn jiàn jūn)に名称を変更しました。八一建军节(bā yī jiàn jūn jié)ともいいます。